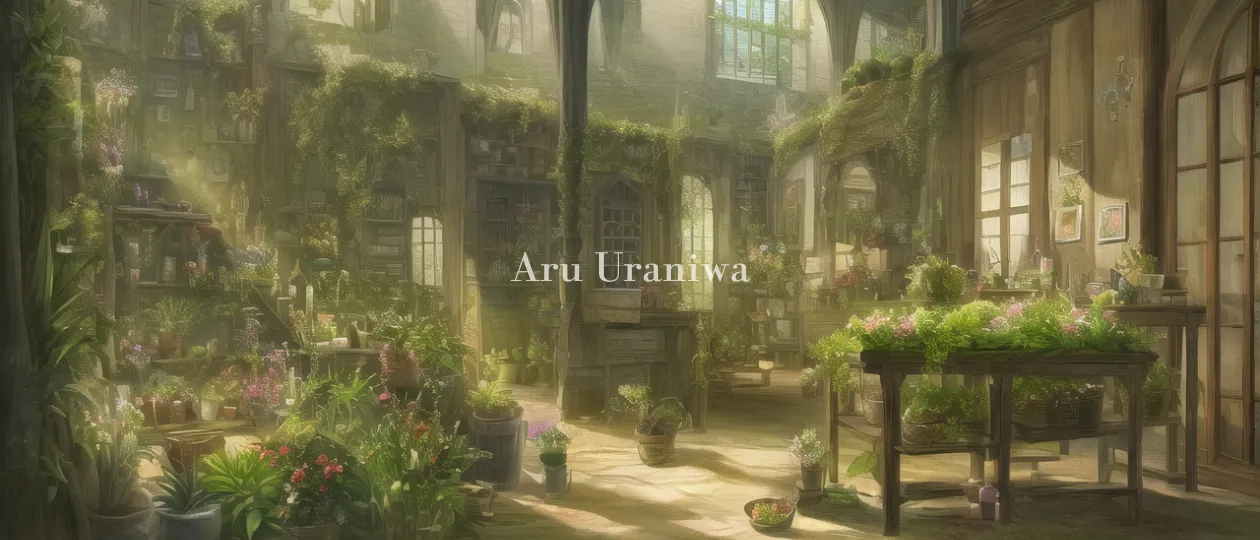カタリナがエイジと暮らし始めて三ヶ月が過ぎた頃。初めてこの家に来て印をつけた壁の前でエイジが呼んだ。
「見てカタリナ! ぼくの身長結構のびたと思わない?」
その印との差に十五センチほど違いがあることをエイジは無邪気に喜ぶ。
僅か三ヶ月で伸びた身長が十五センチ。
エイジとの目線が近くなり、想像していたよりも早いその成長速度にカタリナはゾクリとした。
「……本当だね。子供の成長って早いなあ」
するとエイジはカタリナの顔を覗き込んだ。
「こうして見ると、カタリナと背がそんなに変わらなくなったね。……カタリナって何さいなの?」
「女性に歳を聞くのは失礼なんだよ」
「そうなの……? でもぼくよりちょっとお姉さんってくらいでしょう?」
エイジの意外な質問に、カタリナはふふっと笑った。
「誘導しようとするのもダーメ」
少し垂れ目がちな大きな目を細めてエイジはヘヘッと笑う。
子供のあどけない笑顔だと思っていたのが、顔立ちや雰囲気も少しずつ変わってきている。けれどエイジはまだ気づいていない。
カタリナはそのことを心のどこかで安堵していた。
日中の仕事を終えたカタリナは自宅のテーブルに地図を広げ、向かい側に座っているエイジはいつものように本を読んでいた。
エイジの前に積み上がっている本は分厚いものが八冊。たくさん読みたくて早く読むコツを研究しているらしい。
この子ガリ勉になってしまうんじゃないかしら――と心配しつつ、カタリナは広げた古い地図にバツ印をつけていく。町の中心部にある自宅から西側はもうバツ印でいっぱいだった。
思わず溜息をつくとエイジがこちらを見る。
「どうしたの?」
エイジはカタリナが見ている地図に視線を移した。
「この辺りはもう食料がないんだね」
エイジにぴたりと言い当てられ、カタリナは閉口する。勘の鋭いエイジに嘘やごまかしを言っても仕方がない。カタリナはありのままを伝えることにした。
「そう。もっと足を伸ばすとしたら、食料探しはいつもよりもっと時間がかかるようになると思う」
もし町の端まで探しに行くことになったら、一日で帰ってこられない。そうなれば住処を他へ移すことになるだろう。
「……ねえカタリナ。ここから少しはなれた大きな家にプランターがあったでしょ? 土が入ってたと思うけど、あれって植物を育ててたんじゃない?」
「ああ……、多分そうだと思う」
「野菜とか育てられないかな? ぼくが住んでいた所でもトマトや豆を育ててる家があったよ」
育てられないわけではない。ハローブに人がいた頃は植木もあり、家庭菜園をしている家もあった。けれど今は全く環境が異なる。恐らく育ったとしてもあっという間に枯れるだろう。
「今は難しいと思う。……水や土が劣化してしまったから」
「そうなんだ」
エイジは残念そうに視線を落とした。
最近エイジが植物の本をよく読んでいたのは栽培に興味を持ち始めたからだろう。けれど本のとおりにしてもこの町で植物は育たない。エイジがいくら懸命に育てたとしても。
エイジの落ち込む顔がカタリナの脳裏に浮かんだ。
エイジは夕方になると、よく足の関節を痛がるようになった。
成長が早すぎて成長痛が起きているようだが、カタリナにはどうしてやることもできなかった。
「――っ、いたた……」
「成長痛かな。この間また二センチ伸びたもんね」
金属のダイヤルで日付を合わせる万年カレンダーはもう夏を示していた。
気温があまり変わらないため季節の変化は感じられないが、エイジの成長はどんどん進んでいく。エイジの声も以前より低くなった。
カタリナはベッドに横たわるエイジの膝をゆっくり擦ってやる。
「あまりにも痛かったら痛み止め飲む?」
製造日が不明で効くかどうかも分からない薬だが。
「いい。カタリナがさすってくれるとマシになった気がする……」
「よしよし。痛いの痛いの飛んでいけ〜っ」
「それってどこへ飛んでいくの?」
「遠くの誰か……?」
「かわいそ……」
「じゃあ優しいエイジくんが耐えるしかないね」
「耐えてるよっ」
どれくらい痛いのか分からないが、その横でケタケタと笑っているとエイジはむすっとした顔でカタリナを睨んだ。
するとエイジの腹の虫が鳴く。
「もう夕食の時間なんだ。エイジの腹時計はいつも正確だよね」
「実は時計を食べちゃったことがあって、それ以来時計いらずなんだー」
「えーっ、すごく便利じゃない! じゃあ今は何時なの?」
「え……十七時すぎ、くらい……?」
「全然正確じゃないね」
ぷっと二人、顔を見合わせて笑った。
カタリナはふと不思議な感覚になる。毎日長閑だが無駄な時間を過ごすことはなく充実している。エイジと過ごすこの日常がとても満ち足りたものに感じていた。
最近は保存食をそのまま食べることもめっきり減って、エイジと一緒に料理する。エイジの料理の腕はなかなか良い。これから一人でやらせても大丈夫そうだ。
そしてエイジが一人でこの町を出た後、どうやって自立させるかを考え続けた。
ここから一番近く、比較的大きな街カーラは徒歩数日。もしかしたら向こうの修道院で保護してもらえるかもしれない。エイジの足なら何日かかるだろう。エイジが一人で無事にたどり着くことは可能なのか。
考え始めたら悩みはいつまでも尽きなかった。
「カタリナ。見せたいものがあるんだ」
食料探しから帰ってきてすぐ、エイジに呼ばれたカタリナは後をついて行った。
前に話していた大きな家の庭に着く。そこには三つのプランターから緑の葉が伸びていた。真ん中のプランターはもうすぐ実が生りそうなところまで育っている。
「……エイジが育てたの?」
時々エイジがいなくなると思っていたが、合間を見てここに来ていたらしい。
「うん。どうにか育てられないかと思って、市場で見つけた種をいくつか植えてみた。チェナ豆とラストマト、こっちはアーリカ」
アーリカは唐辛子の見た目で甘いピーマンのような味。カタリナが子供の頃から好きだった野菜だ。
エイジの植えた野菜は順調に育っているようだった。
「いつから育ててたの?」
「これは三日前に植えたんだよ」
怪訝な面持ちのエイジが何を言いたいのか気づき、カタリナは目を逸らしてプランターに目をやる。
「これでも既に三回失敗してるんだ。実がついてようやく成功って言えると思うから、ここからどうなるか分からないけど……ラストマトはここまで育つのに一ヶ月かかるはずなんだよね」
そう言ってエイジはカタリナに視線を向ける。その視線に気づきながら、カタリナはその場にしゃがんでラストマトの葉を指で揺らした。
「……こまめに世話をしてやればこんなに育つんだね」
エイジもカタリナの隣にしゃがんだ。
膝を抱えた腕に頬を乗せ、エイジはカタリナの顔を見つめる。
「僕の背が早く伸びるのは異常だってこと、自分でも分かるよ。……カタリナがいつか話すって言ったから、ずっと待ってる」
何故ハローブは無人の町になったのか。
何故カタリナはここに一人で暮らしているのか。
エイジの目が教えてほしいと訴える。その顔つきはもう、小さかった時のエイジではなかった。
「うん……そうだね。そろそろエイジには話そうと思ってた」
この町に来た頃のエイジは常に不安定な状態だった。夜中に眠ったまま泣くこともあったし、心の傷は簡単には癒せない。だから話せる時期まで待とうと思った。
今のエイジなら話をしても落ち着いて聞くことができるだろう。
カタリナは立ち上がるとエイジの腕を引き、家の影に連れて行ってそこに腰を下ろす。
日陰から見えるプランターの上には、バケツの小さな穴から水が少しずつ落ちるように作られたエイジお手製の水やり器が吊られている。これを考えるのにどれほどかかっただろうと感心した。
プランターからエイジに視線を移すと、エイジの目は真っ直ぐカタリナを見ている。
この町で起きたことやエイジの身に今起きていること。
全て話せば、純粋に慕ってくれるエイジの瞳が恐怖の色に変わるかもしれない。それを想像すると少し苦しくなる。だけど恐怖心が生まれればこの町を離れる決断に繋がる。そしてエイジはきっと、自分の足でこの町を出ていくだろう。
カタリナはようやく決心し、重い口を開きかけた時――。
静けさに包まれた町のどこからか人の気配を感じた。いつも研ぎ澄ませているカタリナの耳は、遥かに小さいが遠くから微音を捉える。それも複数。
カタリナに思い当たるのは国の調査団だった。五年ほど前に一度ここに来ていたが、もう閉鎖した町のことなんて忘れていると思っていた。
もし国の調査団だったら、エイジを保護してもらえる。しかしエイジの口からカタリナの情報が漏れるのは危険だ。どうすべきか。カタリナは敏速に頭を回転させた。
「……エイジ。この家の扉は開いてるから中に入ってて」
「え?」
突然話題が変わって疑問を浮かべているだろうエイジの手を引っ張って立たせると、カタリナは無理やり家の中へ押し込んだ。
もしかしたら国の調査団ではないかもしれない。ひとまずエイジの安全を優先すべきだ。
「カタリ――」
「私が戻るまでここで待っていてね」
困惑の表情を浮かべるエイジに微笑んで、カタリナは扉を閉めた。