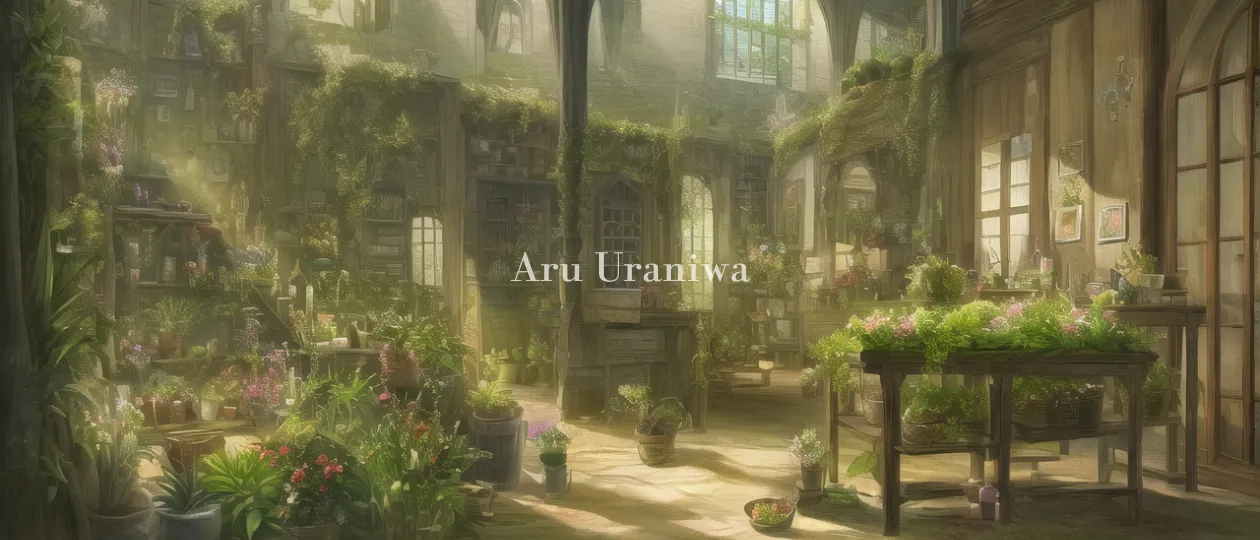『隠れていなさい。決して、見つかってはいけない』
『あなたはどうか、生き延びて……』
どんな思いでそう言ったのか、今となっては分からない。けれどいつまでも消えることのない最期の言葉を、今もなお守り続けている。
それはまるで、呪縛のように――。
暗い部屋の小窓に薄明かりが入り、日の出を知らせる。
目を覚ましたカタリナはゆっくりと体を起こした。昔の夢を見たような気がして、寝覚めの悪い朝だった。
いつものように着替えて日差しを避けるストールを頭に巻き、亜麻色の長い髪を全てストールの中に入れると家の外へ出る。
「おはよう」
朝を知らせるように、少女のような高い声を町に響かせた。
返事や反応がないことは分かっているが、無理やりにでも声に出さなければ自ら声を発することもない。
砂漠に近い乾燥地帯の町ハローブは、日干し煉瓦を積み上げた家や建物ばかり。
砂色の似たような建物が続く通りを抜け、市場があったところや井戸などを見て回る。
ずっと変わらない町並み。変わることのない風景。それらを翡翠色の瞳に映しながらカタリナは町を歩いた。
昨日は通らなかった路地に差し掛かり、廃屋の窓際に転がっている遺体を見つける。
カタリナは辺りを警戒しながらゆっくり近づいて遺体の状態を確認した。
最近亡くなったような老人の遺体。いつからこの町に入り込んでいたのか分からないが、行く宛てもなく住み着いたか自殺志願者か。
カタリナは遺体をそのままにしてそこを離れた。
小さい町だが朝から歩いて一周するには陽が天頂を過ぎる頃になる。
毎日カタリナは町に変化がないか見て回っていたが、今日はいつもと違った。
東の町外れまで来たところで、今度は動くものが遠目に見えた。動物か何かが。
カタリナは耳を澄ませ、辺りを警戒しながら身を潜めた。
建物が途切れた先の、町の外を囲むように立てられた柵の外へ目を凝らす。
そこに、目を擦るような仕草をする――子供。
まさか、とカタリナは目を大きく見開いた。辺りに他の人間は見当たらない。子供は一人だ。
警戒心を忘れたカタリナは足早に子供の元へ近づいた。放心しているのかその場に立ち尽くす、黒髪の少年。
「何でこんな所に子供が……」
カタリナの声に反応した子供はゆっくりカタリナを見上げた。琥珀色の目は泣き腫らしたようで、白目も充血している。背丈から見て七、八歳くらい。
カタリナは少しかがんで少年の目線に合わせ、ゆっくりした口調で尋ねた。
「お父さんか、お母さんはいないの?」
すると堰を切ったように少年の目は涙が溢れ出し、嗚咽を漏らし始めた。
カタリナは辺りを見回したがこの少年以外に人の気配はない。
ハローブの周辺には徒歩数日かかる街がある他、ずっと東の方へ行けば移民が住む集落などもあるが、子供一人でここまで来られる距離ではない。
少年は何らかの理由でここに捨てられたのだ。
ハローブは閉鎖された立入禁止の町だから。
少年の足元に落ちているリネンのブランケットを拾って砂を払い、少年に頭から被せるとカタリナは少年の細い体を抱き上げた。
軽い。骨と皮といってもいい。少年の体にはほとんど肉がなく、痩せこけていた。
「まずは朝ご飯を食べようか」
自宅からここまで既に一時間歩いてきた。
軽いとはいえ、一時間も少年を抱いて歩くほどの体力はカタリナにない。
近くに井戸がある適当な家に目星を付け、カタリナは少年を下ろした。
「ちょっとここで待ってて」
木の窓を落ちていた煉瓦で何度か叩くと壊れ、そこから中へ入って部屋を物色した。
ハローブの食料品供給は行商隊や他の街から入ってきていたため、それが途絶えると食料に困る。過去に紛争があって供給が途絶えたこともあった。
その教訓を得て、大抵の家や店には魔法で保存された食料や缶詰などが備蓄されている。
それを見つけたカタリナは玄関の扉を開けて、外で待たせていた少年に「入っていいよ」と声をかけた。
ところが少年は目を丸くしたまま固まっている。カタリナを泥棒か何かだと思っているのだろう。
確かにここが普通の町ならこれは泥棒行為だと思い、カタリナはふっと笑みを零した。
「誰も住んでないから大丈夫だよ」
少年を家の中へ入れると、カタリナは脚の短いテーブルに積もった埃を雑に払い、見つけた保存食をテーブルに並べていく。
「私はカタリナ。君は?」
「……エイジ」
エイジは掠れた小さな声で返事をした。
カラカラに喉が乾いているようで、唇もひび割れている。
カタリナは棚からスプーンを見つけて布で拭き、保存食の箱と缶詰を開けて匂いをかいだ。
野菜のスープとパンだが匂いに問題はなく、味見をしてみても違和感などはなく美味しいと感じる。何十年も前のものだが。
「じゃあエイジ。これゆっくりよく噛んで食べて」
床の敷物に腰を下ろしたエイジは、渡されたスプーンを持つとすくったスープを恐る恐る口に入れる。
すると、飲み込んだのか分からないうちに次々とスプーンを口へ運んでいった。相当空腹だったのだろう。
「ゆっくりね。お腹がびっくりするよ」
エイジが食べている間に、カタリナは近くの井戸からバケツで水を汲んできた。
長年管理されていない井戸だから水が薄茶色に濁っている。
浄化魔法が使えれば汚れた水を奇麗な飲める水にできたが、そのような能力を持つ者は稀だ。
魔法を使えないカタリナは水を濾過した後、魔法の原理で動く加熱魔導具を見つけ、まだ動力が生きていたからそれで沸騰させた。
しばらく使った後に魔導具は動かなくなってしまったが何とか煮沸はできただろう。それでも水は透明にはならず、薄っすら黄みを帯びた状態だった。
すっかり食べ終えてしまったエイジの前に、カタリナは煮沸した水の入ったコップを置いた。まだ熱が冷めていないので正確には湯である。
「水はこれを飲んで。井戸の水を煮沸殺菌してみたんだけど、うーん……どうだろ」
水は薄っすら黄みを帯びている。エイジはそれを見つめたままで、コップに手を付けようとしない。
飲めば腹痛や下痢をするかもしれないが、脱水状態が続くのも危険だ。
いずれにせよ、ハローブにいる今はこれを飲むしかないのだ。
カタリナは子供がここにいても長く生きられないことを分かっていたが、衝動でエイジを拾ってしまった。ひとまずこれから先のことは後で考えるしかなかった。
なかなか手を付けなかったエイジは、しばらくして薄く色のついたコップにそうっと手を伸ばした。
すると中の水が一瞬で透明になる。
カタリナは何度も目を瞬いて、透明になった水をじっと見つめた。
「今の、何やったの?」
カタリナは大きな目を更に大きくして、コップを手に取った。
「わからない……」
エイジも何故そうなったのかよく分かっていないようで戸惑っている。
カタリナはためらいもなくその水を口に含んだ。生臭さや変な味はしない。真水だった。
「美味しい……。エイジ、もしかして浄化魔法を使えるの?」
「……使ったことない」
今度はバケツごとエイジの前に置いた。
「エイジ。これ浄化してみて?」
バケツに残った薄茶色の水を前に、エイジは困惑の表情を浮かべる。
「やり方がわからないよ……」
「多分エイジは浄化魔法が使えるんだと思う。だって濁った水が一瞬で透明になったんだよ?」
バケツの水を見つめていたエイジはバケツを抱いたり揺らしたりしてみた後、ちらりとカタリナの方へ視線を向けた。
その目が見逃してほしそうに訴える。
「魔法は願いながら実行するって学校で教わらなかった? 強く願えばきっとできるから、やってみて?」
カタリナがにっこり笑顔を見せると、エイジのごくりと唾を飲む音が聞こえた。
エイジはバケツを両手で抱えたまま中を覗き込む。バケツをつかむ手は随分と力が入り、頭を中へ突っ込むような勢いで水を睨み付けている。
あまりに真剣なエイジを見て、カタリナははたと思う。
もしかして強要したように聞こえてしまったかもしれない。浄化できなければこれを飲まされると思っているのでは。
カタリナはもし浄化できなくても大丈夫だと言おうとした時、エイジがぱっと頭を上げてカタリナを見た。
その顔は僅かに緊張の解けたような表情で、カタリナもバケツの中を覗き込んだ。
水が透明になっている。
すくって飲んでみれば先ほどと同じ、真水だ。
「わ、本当に浄化できたよ! すごいねエイジ!」
カタリナはぱっと明るい笑顔になってエイジの頭を撫でた。
「どうやったの?」
エイジは面映い顔をしてカタリナを見上げる。
「……ぜったい飲みたくないって思っただけ」
あれから歩けるというエイジと帰路に就き、空き家を物色しながら自宅へ連れ帰った。子供の衣服もカタリナの家には置いていないため、他所の家から調達した。
その間にエイジの家族のことや、どんな所に住んでいたのか尋ねた。
「家族は父さん母さんと兄ちゃんがいる。父さんが病気でねこむようになって、いつも家に食べ物がなくて……ぼくは働いてた」
エイジは十歳。集落に住んでいたようで、学校は一年前まで通っていたらしく文字の読み書きができる。
仕事は採掘現場で重いものを運搬していたという。児童労働は長時間拘束されて低賃金。まともな食事もなく、食べられて一日一食だというから体力もなかっただろう。
「そう。エイジはずっと家族を助けてきたんだね」
「昨日……、母さんがおり物を売りに行くって夕方いっしょに荷車で出かけた。そのまま荷車でねて……起きたらぼく一人だった……」
またエイジは目に涙を浮かべる。親に捨てられた現実をすぐには受け入れられないだろう。しかし親元に帰れるという希望は与えない方がいい。恐らく口減らしのためにここへ置いていかれただろうから。
カタリナはこの町、ハローブに人が住んでいないことをエイジに話した。
昔、多くの人が他所へ移住して今は無人の町になっている――と。
「食べ物は空き家とか店から探して取ってこないといけないの。でも心配しないで。この町にあるものは全部捨てられたものなの。それを拾うだけだから泥棒じゃないんだよ」
エイジが罪悪感を持たなくてもいいように泥棒じゃないことを強く主張すると、エイジは黙ったままこくんとうなずいた。
昼過ぎにカタリナの自宅へ着くと早速エイジに昼食を食べさせた。
エイジは黙ったままずっと大人しかった。この現実を受け入れるため気持ちの整理をしているのかもしれないが、悲しんでいる暇はない。
「さ。エイジにはやってもらうことがあるよ」
食べ終えた空の缶詰やスプーンはそのままに、大きなバケツを持ってエイジを井戸のある場所まで連れて行った。
飲料水や生活用水は全て井戸から汲んでこなければならない。
「また井戸の水を家まで運んで、エイジに浄化してもらいたいの。飲めるようにね」
井戸の使い方を教わったエイジはカタリナと一緒に水を家まで運び、浄化魔法をかけられるまで再びバケツとにらめっこすることになった。
魔法の才能は突然現れたりする。学生の時にそう教わったがエイジもそれに該当するだろう。
親元にいた頃は水に困ったことがなかったらしく、浄化する必要に迫られたこともないからその才能を見いだす者もいなかったようだ。
日が傾いた頃、エイジの目がぼんやりし始めた。
突然自分の身に起きた状況についていけず、緊張が続いて心身ともに疲れたのだろう。
今にも寝てしまいそうな様子で、カタリナは早めに夕食を食べさせて濡らしたタオルで体を拭いてやると、用意した寝床にエイジを寝かせた。
部屋の絨毯の上に両親が使っていたマットを敷いて上からシーツを被せただけのベッドだ。
横になったエイジの隣に腰を下ろし、カタリナは様子を窺った。
「一人で眠れる?」
エイジは小さくうなずくと、そのまま反応がなくなった。
カタリナは眠りに落ちたエイジを観察する。
十歳というには随分と体が小さいように感じる。栄養不足で成長が遅いのかもしれない。明日はもう少し食べさせる量を増やしてみよう。
自分の部屋へ戻ろうと立ち上がりかけて、カタリナは服が引っ張られることに気づく。エイジの手が、カタリナの服をつかんでいた。
頼れる大人がいなくなる恐怖を覚えて不安なのかもしれない。カタリナはその手を優しく包んだ。
人肌に触れるなんてどのくらい振りだろう。その手はとても温かかった。
エイジの手をそっと離して自室へ行き、寝る準備をして戻ってきたカタリナはエイジの隣にマットを敷いて横たわった。
あどけない寝顔を見つめながら、カタリナはこれからのことを考えた。
エイジをこれからどうするべきか――。