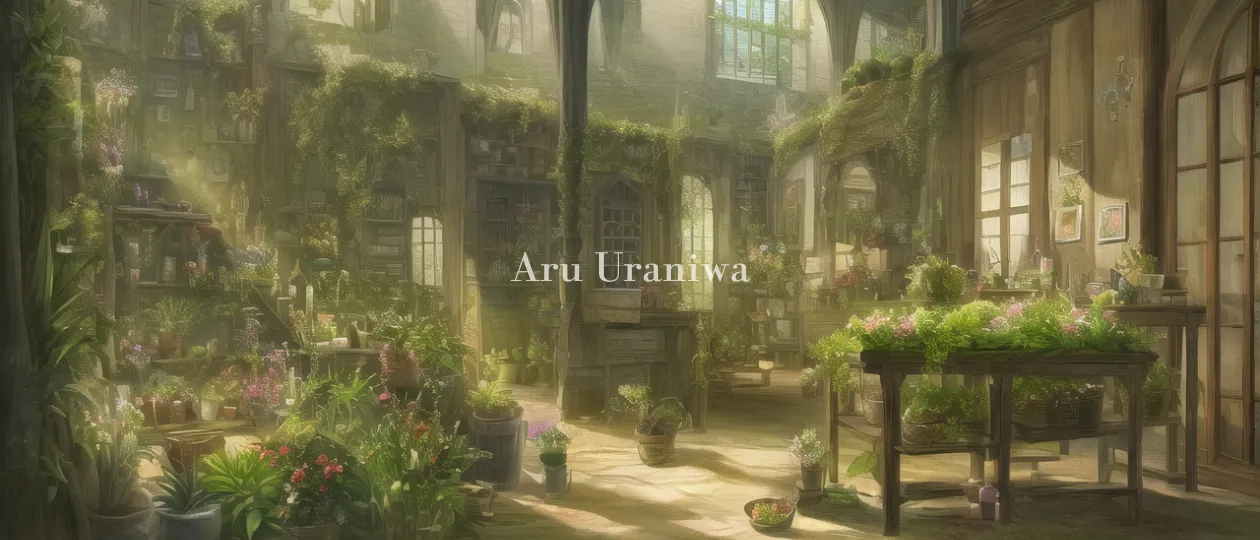カタリナはストールを深く被って顔を隠し、足早に家へ戻った。
知っている人全員に会ったわけじゃない。けれど。
自室に置いてあった手鏡をそっと覗く。そこにはいつもと変わらない自分が映っている。少し幼い顔のままの、十八歳の顔。
いつもどおりの自分の顔は何もおかしいところなんてない。なのにおかしいと感じるこの状況が恐ろしくて、カタリナは鏡を伏せた。
それからも母の代わりに家事をしながら、カタリナが時々隠れて外へ出た。
ハローブの死者数は増え、移住する人が増えていると耳にする。
町を出ていくにも輓獣車か、荷物を運ぶロバやラクダが必要。しかし移住者が多くて、車も動物も足りない。最低限の荷物だけ持って町を出ていく人がどんどん増えた。
それから後に、国から避難命令が出された。
もうその頃には両親とも加齢が進んでいて、あまり歩ける状態ではなかった。
「ねえお願い、二人も町を出て避難して……!」
カタリナは両親に懇願したが、二人とも首を横に振る。
「もう……何日も歩いて隣町まで行く体力はないよ」
「わたしたちはここに残るわ。カタリナ、あの引き出しにお金があるから、必要なだけ持って行って」
二人は町を出ることを望んでおらず、カタリナ一人で避難するように言う。
既に老人のような姿の両親と、全く姿の変わらないカタリナ。彼女が魔法発現者と断定するには十分だった。けれど両親はそのことに一度も触れない。
ハローブに広がった災厄が町そのものに影響しているのか、それともカタリナを中心に影響を及ぼしているのか分からない。
もし後者なら、カタリナが他の町へ移ってもそこで同じことが起こる。そしてカタリナの一番近くにいるのは両親だ。
「……誰か呼んでくる。お父さんたちを一緒に連れて行ってくれる人を探してくるからっ」
立ち上がろうとしたカタリナの手を父がつかんだ。
「いいんだカタリナ。父さんも母さんもこの家を離れたくない。最期までこの家で過ごしたいんだ」
「だって、私といたら……!」
これ以上老化が進んだら、二人は。
「お前は何もしていない。何も悪くない。絶対に」
「そうよ。あなたは平和主義で人を傷つけたりできない子だもの。わたしたち自慢の娘よ」
きっと悪い何かに巻き込まれてしまったの。そこに居合わせたタイミングが悪かったの。
そう言って母はカタリナの背を撫でる。
「だからお前は隠れていなさい。決して、見つかってはいけない」
「あなたはどうか、生き延びて……」
こんな状況になっても二人はずっとカタリナを信じていた。
どうしてこんなことになってしまったのか。熱い雫がカタリナの頬を伝って落ちる。母は子供を慰めるようにカタリナの頬を拭って抱き寄せた。
カタリナが母の胸で泣いたのはそれが最後となった。
何度も魔法が止まるよう願った。二人の老化が止まるよう祈った。けれど、食事を取れなくなっていった父は衰弱するように逝き、しばらくして母も眠るように逝った。
二人の反対を押し切ってでも調査団に話していれば、魔法を止める術が見つかったかもしれない。
カタリナが処刑されていれば、町はこんなことにならなかったかもしれない。魔法使用者が死ねば魔法も止まるのだから。
目の前で二人を看取ったカタリナは一切の食事を受け付けなくなった。
もう動きたくなかった。何もしたくなかった。腹も減らず喉も渇かない。
目を閉じて次に目を開いた時、父と母がいてくれたらいいな。そう願いながら眠りに就き、いつもと同じように目覚めて絶望する。
どうせ目を覚ますなら、母が朝食を作る音を聞いて目を覚ましたかった。朝から新聞を読む父の話を毎日聞かせてほしかった。
父も母もベッドの上で目覚めることはもう二度とない。
カタリナは毎日涙が出なくなるほど泣いて、二人の亡骸の前で呆然と座り込んでいた。
その森閑とした室内に、突然玄関のドアノッカーが鳴り響く。
「すみません、誰かいらっしゃいますか?」
男の声がして心臓が跳ねた。
カタリナは音を立てないよう廊下にある地下収納庫へ急いだ。
もう近隣の人は死んだか移住したかで誰もいない。ここを訪ねてくるような人といえばもう調査団くらいしか思い当たらない。
急いで狭い空間に身を隠し、扉をそっと閉めて様子を窺う。
ドアノッカーを叩いても返事がないと分かったのか、玄関扉を無理矢理開けて中に人が入ってきた。
「調査団の者です! 誰かいませんかー!?」
二人の足音がし、各部屋を確認している音が伝わってくる。生存者がいないか確認しているようで、近づいてくる物音にカタリナは身をすくめた。
「こちらに遺体が二名。この家の住民と思われます」
「そうか……。よくもこんな大勢の命を奪えたものだな……」
「ええ本当に……。あ、そちらは……?」
足音が廊下の収納庫の方へ集まってきた。
「床にある収納庫じゃないか?」
「地下室があるかもしれません。そこも開けてみますか」
カタリナは震える手を握りながら息を殺した。
収納庫の扉がキィと音を立てて開き、光が差し込んで中がはっきり見えてくる。収納庫の梯子の下には複数の保存食や日常使う消耗品などがぎっしり詰まっていて、人が入れる空間はなかった。
「ただの収納庫のようだね」
「そのようですね。……それじゃあご遺体はお二人のようなので運び出しましょう」
カタリナは地下収納庫に物がたくさん入っていることを思い出し、自分の部屋のクローゼットに身を潜めていた。そこから両親が運び出されていくことを知って、静かに涙を流し、震える唇を噛んだ。
二人に別れを告げることもできず、調査団の彼らに助けを求めることもできない。
隠れていなさい。見つかってはいけない。疑わしき者は罰せられる。
両親の言葉がカタリナをそこに押し止めた。
カタリナはそれからずっと隠れ続けた。哀傷と恐怖を抱え、孤独なままずっと。
空腹にならないから飲食もせず、眠って起きて動くことすらなかったのに筋力の衰えもない。
一ヶ月ほど経って、カタリナは自分が餓死しないと分かった。
長きに渡り滞在していた調査団は調査を終えたのか、住民が避難した後この町を撤退したらしい。
人や生き物のいなくなった町は、何も音がしない夜の静寂のように静まり返っている。
生まれ育ったこの町でカタリナは初めて音のない世界を知った。
カタリナは静かに家の外へ出た。自分の衣擦れの音と歩く音だけが町に響く。
町の端から端まで何時間も歩き回った。歩いて、歩いて、南西の町外れまできて、ようやく見つけた。
集団埋葬されたと見られる小さな石を置いただけの簡易墓地。
数え切れないほどの石がカタリナの視界に飛び込む。全ての石が、この事態を引き起こしたカタリナを見ているように感じた。
それらの石には名前の分かる者だけ名が刻まれている。
浅い呼吸を繰り返しながら込み上げるものを飲み込んで、一つ一つカタリナは石を確認していく。端の方まできてやっと、父と母の名が彫られた石を見つけた。
二人の名が刻まれた石に指で触れると、カタリナは跪いて頭を地につけた。
「ごめ……なさ……、ごめんなさい……、ごめんなさい……うう、あああああ……っ!」
墓にすがりついて嗚咽する。
奪ってしまった。たくさんの人の未来を。
両親は最期まで信じてくれたのに、これほどの数の人々を不幸にした。
カタリナは全ての選択が間違いだったのではと思う。
隠れて逃げて、自分が生き延びたことに意味はあったのだろうか。こんな災厄を呼び起こした魔女のような女が生きる意味は。
自分を信じて守ってくれた両親はもういない。
多くの命を失った悲劇の町ハローブはいつか、地図上から消されるだろう。
それでもここに生き続ける意味はあるのか。
誰か、教えて――。