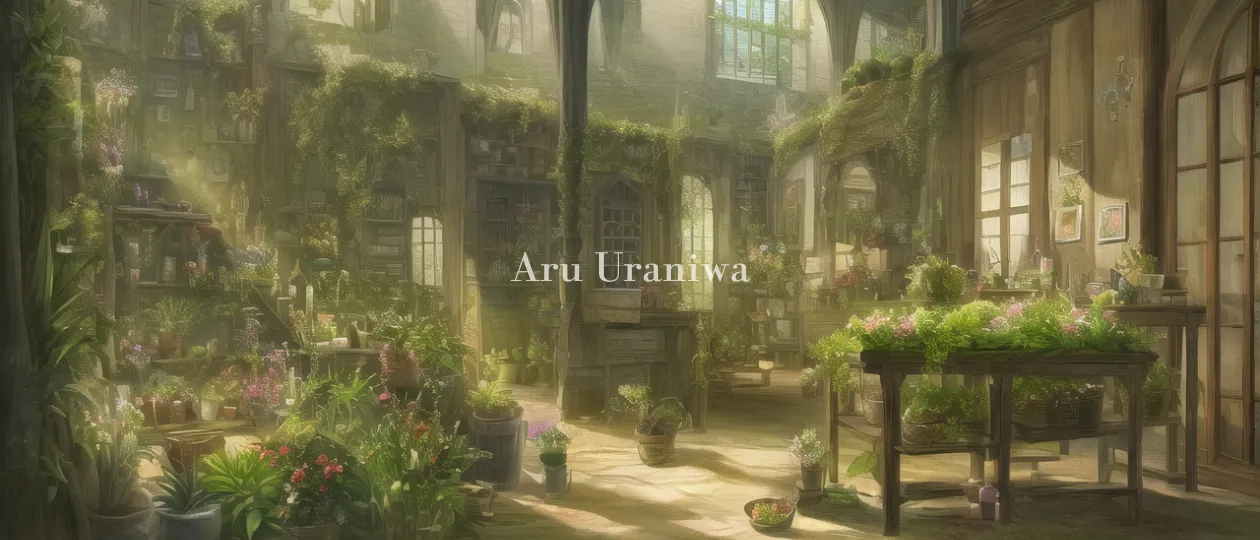朝、目が覚めるとカタリナはいつも先に起きていてベッドにはいない。
カタリナはいつ寝て、いつ起きているのか。
エイジはまだカタリナの寝顔を一度も見たことがなかった。
エイジはぱっと体を起こして着替えを手に取った。いつもぐっすり寝かせてくれるから体が軽い。
空腹で体がだるく、毎日疲れていたあの日々を少しずつ忘れかけている。
家族はもう自分のことを忘れてしまっただろうか。
エイジは時々家族のことを思った。
『お前は本当に役立たずの穀潰しだね……!』
いつも両親に言われていた言葉だった。
年子の兄は要領が良く、仕事先の人に目をかけてもらえるのか時々食料をもらって帰ってくる。そんな兄とエイジはいつも比べられた。
そして兄の髪は父譲りの赤茶色。母は白茶色で死んだ祖父母も茶系の髪色。黒髪はエイジただ一人。家族の誰にも似ていなかった。
寝ている時に両親の喧嘩で目覚めた時、聞いてしまった。
母の不貞を疑う父が母を罵り、いつも来る行商隊の男が黒髪だったとなじる。
エイジはその時初めて、父親が自分の本当の親でないことを知った。だから父は自分を冷たい目で見るのだ。
家で何をやっても愚図だ、のろまだと怒られ貶され、褒められたことは一度もない。
仕事場で殴られて両親に体が痛いと訴えても、クビになるようなことは絶対するなときつく言われるだけ。
エイジはとにかく怒られないように、親の顔色を見ながら常に萎縮していた。特に母へ神経を使った。
母が父から非難されるとその矛先はエイジに向く。
お前のその髪のせいで――!
母は何かあると黒髪を罪の象徴のように言った。
家のことは集落の中で知らぬ者はいない。母は立場がなく働けなくなった父に代わって頭を下げて僅かな仕事をもらい、家では寝る間も惜しんで作った織物を定期的にやってくる行商隊に売る。
これまで家がどれほど追い詰められた状況だったのかエイジにも分かっていた。
どんなに苦しい生活でも、愛してもらえなくとも、それでも帰る場所があるだけで存在を許されていた。そう、思っていた。
捨てられたあの日。最初に自分の視界に映ったのはまだ日が昇っていない薄明の空。濃紺から橙色への鮮やかなグラデーション。
あの空の下で、エイジは家族にとって必要のない人間なのだと突きつけられた。
――がんばりが、足りなかった……? 家族の役に立てなかったから? 父さんの子じゃないから?
どうして。いらないならどうして産んだの……?
どうすれば良かったの……。
まぶたが熱くなるのを必死にこらえる。
泣くな。泣くな。泣いたらやかましいとどなられる。物置にとじ込められる。
ああ……でももう、自分をおこる人はどこにもいない――。
「エイジはえらいね。よく頑張ってるよ」
眠っている時にカタリナが頭を撫でてそう言ったのをぼんやり覚えている。
カタリナは何も言わなくても手を繋いでくれる。
勉強を頑張れば、頭を撫でてたくさん褒めてくれる。
家族の誰もしてくれなかったお休みのキスをしてくれる。
泣いたら抱きしめてくれる。
心の痛いところをカタリナが痛くないようにしてくれる。
――エイジは賢いね。
魔法の才能があるからこれからもっと伸びるよ。
どうしたの? ああ、ここはね、先に割り算してから掛けると計算しやすいよ。
わ、すごい。エイジの発想にはいつも感心するなあ。
どうしてそんなに褒めるのか。どうして怒らないのか。エイジはいつも不思議に思っていた。けれど、カタリナの言葉はいつも寝る時に思い出すと心が温かくなった。
エイジは朝の着替えでズボンを引き上げると、丈が短く腰回りもきつくなっているように感じた。
服が小さくなったことをカタリナに話せば食料探しのついでに服も探すことになった。
もう近場で子供の服が手に入らなくなり、服を探しにカタリナと少し遠出をする。
「ねえカタリナ。あそこは何?」
エイジが指差したのは、遠目に見える北の町外れにある建物。遠目に見ても町の建物と比べて老朽化が激しく感じる、少し不気味な場所だ。
「あれは修道院だよ」
高い壁に囲まれていて、修道院という建物は外からあまりよく見えない。
俗世との縁を断ち切るためか、もしかしたら修道士が逃げられないようにしてあるんじゃないかとカタリナは言う。
外に出られないなんて修道院って刑務場みたいだとエイジは思った。
「埋葬された遺体もたくさんあるらしいから、死んだ人の霊がたくさんいるかもね」
生涯を終えた修道士は修道院内の墓地に埋葬される。だが今は墓地を管理する人間が誰もおらず、置いていかれた遺骨が嘆き悲しんでいるかもしれない――と、カタリナは頬に散らばるソバカスの愛らしい顔を悲しそうに歪ませて見せた。
エイジは本に描かれていた目のない幽霊の挿絵を思い出して背筋がぞくりとした。
「れいって、ゆうれい……!? ゆうれいって本当はいないんでしょ?」
エイジは表情を硬くしてカタリナを見上げる。
「見えないから分からないけど実際はいるかもよ? 私は見たことないけど、あそこは不気味だから近づきたくないのよね」
「そ……そーなんだ。じゃあぼくも行ーかないっ」
エイジは本の物語にでてくるお化けや霊のような存在が苦手だ。
子供を怖がらせて言うことを聞かせるための、大人の陰謀による作り話であることをエイジは知っていたが、怖いものは怖かった。
それからカタリナと服を探してようやく民家で子供服を見つけた。
大きさを見ながら試着していく。前の服と比べるとかなり大きめだが、これならしばらく着られそうだった。
これはどう? とカタリナに聞けば、じっと見つめているだけで返事がない。
「カタリナ……?」
「あ、ごめん。この服にしようか」
「うん。ぼくは着られれば何でもいいよ」
何でもという言葉にカタリナが反応した。
「じゃあこれは?」
ピンク色のひらひらしたワンピースをエイジの体に合わせた。
「これは女の人の服じゃない?」
何故女性物を合わせるのかと思ったが、髪型のせいかなとエイジは思う。
髪はここに来てから既に十センチほど伸びていて、先日カタリナがエイジの前髪を切った。額の真ん中辺りに鋏を合わせ、ジャキッと水平一直線に。
カタリナが一瞬申し訳なさそうな表情を浮かべたけれど、どうせ誰も見ていないのでエイジは特に気にしていない。
しかし後ろは肩に付きそうな長さ。そんなエイジにワンピースを合わせるものだから、女の子みたいだとカタリナは言いたいのだろう。
「何でこれを女の服って決めつけるの?」
「だって女の人しか着てるのを見たことないし、ぼくは男だし……?」
エイジは恥ずかしそうに、体に合わせていたピンクのワンピースから一歩後ろに下がって体を離した。カタリナに女の子のようだと思われるのはなんだか嫌だった。
別に誰も見ていないのにそんなに恥ずかしい? と言いたげな顔でカタリナは首を傾げる。
「不思議だねえ。女はワンピース、男はズボン? そんなの誰が決めたんだろうね?」
「え、と……それは……んー……」
答えに詰まったエイジは首を捻る。
「たくさんの白の中に一つだけ黒が混じると異質に見えるでしょ。集団の中で生きていると、人は多数派に同調しやすくなるの。自分はこれが好きだと思っていても周りがおかしいと指摘すれば、そうかもしれないと考えるようにもなる。つまり、これを女の服だと思ってるエイジも周囲に植え付けられた考えなんだよ」
時々カタリナは難しいことを言う。
エイジはカタリナの言葉をよく考えて答える。
「じゃあ、男の人がピンクのワンピースを着てもおかしいって言われない町とか国があるの?」
「きっとあると思うよ。私は他の国を見たことがないんだけど、世界は広いんだって」
「そうなんだ……。他の国かあ。見てみたいな」
エイジは遠くを見るように目を細めた。
外国なんて考えたこともなかったけれど、いつか行ける機会があるんだろうか。それにはまずお金を稼げる大人にならないといけない。
もし大人になった時、カタリナも外国に行ってみたいと思っていたら一緒に行けるだろうか。
カタリナはここにいないといけないって言ったけど、それはいつまでだろう。カタリナの仕事なんだろうか。でもずっとではないと思うし、少しくらいなら旅行へ行ってもいいと思うのだ。お世話になったお返しと言えばカタリナは聞いてくれそうな気がする。
早く大人になりたい。カタリナの役に立ちたい。エイジは純粋にそう思った。
今日の夕食はエイジが一人で作る。かまどに火をつけるのも魔法でできるようになった。
覚えたレシピを試したくて魚の缶詰や調味料を鍋に入れて煮込んでいると、横からカタリナが覗き込む。
「いい匂いだね」
「カタリナ味見してみて」
エイジはスプーンをカタリナの口に近づける。トマトと香ばしいスパイスの香りを吸い込み、カタリナはふうふうと冷ましながら口に入れた。
「美味しい。味付け上手だねエイジ」
「良かった! これならパンに合うかと思って」
「うん、パンも美味しくなりそうだね」
エイジは二人分を皿へ盛っていく。一つの皿だけ量を多く。カタリナにたくさん食べてもらいたかった。
取り分けていると、カタリナがエイジの手を制止した。
「エイジ、私はそんなに食べられないよ。その半分も無理だから残りはエイジが食べて」
「カタリナ……」
エイジは不服そうな顔でカタリナに目をやる。
「ぼくがここに来て、カタリナが食事をするところをほとんど見てないよ。食べてくれても味見程度じゃない」
「いや、密かに食べてたりするんだよー。今までそんなに食べてなかったから、一日三食なんて私には多すぎて」
「うそだ……。水だってあまり飲まないじゃない。ぼくに食べさせないといけないから食料の心配をしてるんでしょ? だったらぼくも食べる量を減らすから……お願い、食べてよ」
持っていた鍋を置いて、エイジは強く訴えるようにカタリナの手を握る。
「エイジ。食料は心配しなくていいよ。この町は昔、人がたくさん住んでたから探すところはまだまだたくさん残ってる」
カタリナは微笑んで見せるが、それはエイジを安心させるためのもの。カタリナがエイジのために食料を節約している。エイジはそれがとても心苦しく感じた。
飢餓で苦しむ家族はエイジに食べ物を分け与えたりなどしなかったのに、他人であるカタリナは無条件にエイジを慈しむ。
エイジの目は次第に赤くなり、琥珀色の瞳が潤んでいく。
「食べなきゃカタリナがたおれちゃう……。そんなのダメだよ……」
「大丈夫。少ないけど食べてるから心配しないで。今日はいつもより食べられそうな気がするから、しっかり食べるね。ありがとうエイジ」
零れ落ちそうなエイジの涙を指で拭って、カタリナはそれをぺろっと舐めた。
「エイジの涙しょっぱいねー」
「もう……なみだより水を飲んでよ」
「いやいや、塩だって大事なんだよ?」
その日はカタリナが料理を全部食べてくれて、何度も何度も美味しいと言ってくれた。格別の夕食になった。
またカタリナに喜んでもらいたい。いつもカタリナに笑顔でいてほしい。
エイジの活力の源は次第にカタリナが中心となっていった。